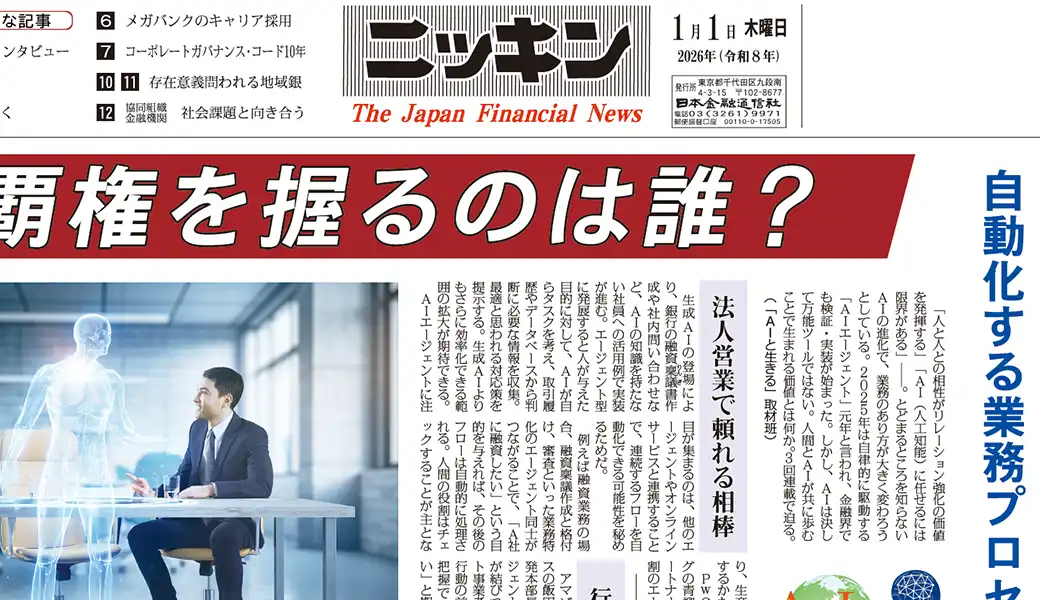社説 付利変更は納得感ある説明を
日本銀行は、経費削減などに取り組む地域金融機関を支援する「特別当座預金制度(特別付利)」を急きょ見直した。新型コロナ対応オペの利用急増で付利額が想定より大幅に上回るためだが、同制度は9月に適用が始まったばかりで唐突感が否めない。経営効率化に向けた金融機関の改革機運を後退させかねず、日銀は見直しの妥当性を丁寧に説明すべきだ。
特別付利は経費削減や経営統合など要件を満たす地域金融機関の日銀当座預金金利を年0.1%上乗せする制度。多くの金融機関に経営基盤強化のインセンティブを与え、経費率(OHR)改善を広く促した。実際、あるシンクタンクの試算では地域銀の約8割が上乗せ金利を受け取る。
今回の制度変更はコロナオペの延長などで金融機関の日銀当預残高が膨らんだためとされる。付利の支払いが当初の見積もりを大きく上振れする見通しとなり、付利対象額に新たな上限を設ける。だが、コロナオペ需要の高まりは十分予測できたはずで、判断に至った経緯が釈然としない。
懸念されるのは、構造改革を進める金融機関の意欲を削ぐ可能性があることだ。日銀は経営への影響に配慮し、21年度は見直し前までの対象残高に応じて付利する経過措置を取る。ただ、付利の対象となっている22年度までを見込んで収益見通しを立てている金融機関が多く、修正を迫られる先も出てこよう。
上場する地域銀行・グループの21年4~9月期決算は約9割が増益となったが、与信コストの減少要因が大きく、本業の収益環境は依然厳しい。背景には長引くマイナス金利政策があり、特別付利導入は「収益に及ぼす悪影響への配慮」(エコノミスト)という意味合いもあったはず。金融界との間で生じた“溝”を深めないためにも、日銀には納得感のある説明を求めたい。2021.11.26
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。