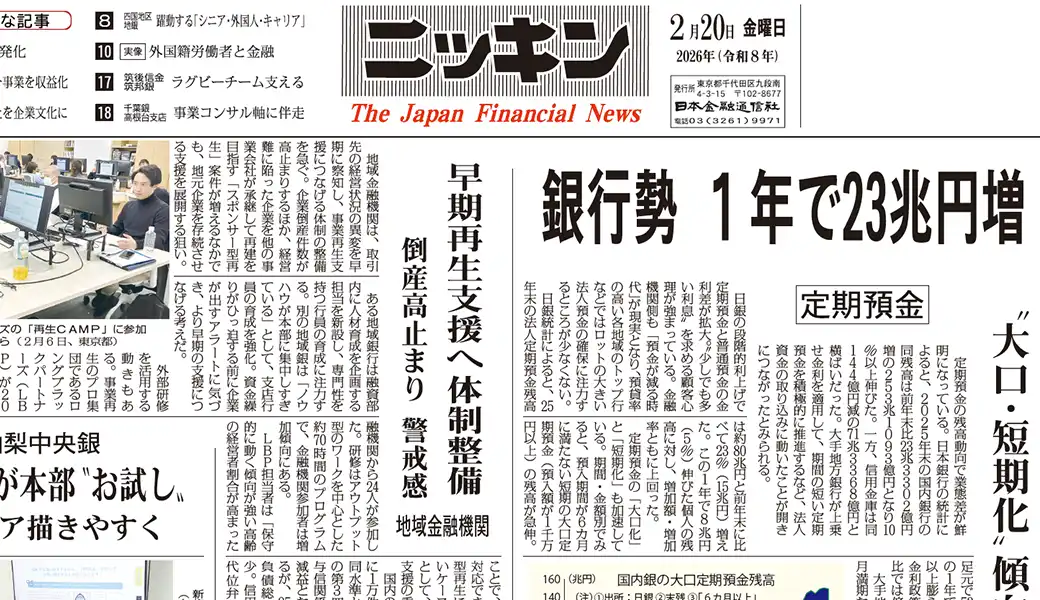社説、追加緩和で仲介機能損なうな
日本銀行は7月の金融政策決定会合で、物価上昇の勢いが弱まりそうな場合は予防的に追加緩和する方針を示した。米欧の中央銀行が緩和に積極姿勢を示していることや米中貿易摩擦を踏まえ、円高・景気下振れへの対処は必要だろう。だが、金融機関の経営に悪影響を及ぼしている異次元緩和の追加策は慎重な判断が求められる。特に劇薬であるマイナス金利の深掘りは金融仲介機能を損ないかねず、避けるべきである。
黒田東彦総裁は追加緩和について「手段はいくつもありうる」と述べ、従来よりも前向きな姿勢を強調した。米欧の緩和競争をけん制したものだが、その直後に米中対立が再び激化。人民元安による円高圧力が強まり、追加的な措置を迫られる情勢に近づいているのは確かだ。
しかし、さらなる緩和が負の側面を強めないか十分に見極める必要がある。約6年半に及ぶ異次元緩和は金融機関の体力を奪い、2018年度は地域銀行の7割が減益決算となった。日銀の政策委員が「副作用によって効果が損なわれてしまう可能性も念頭に、慎重な点検が重要」と指摘するのも当然だ。
そのため市場関係者の間では追加緩和する場合、まずはゼロ%に誘導している長期金利の許容範囲(上下0.2%程度)の拡大にとどめるとの見方がある。その際も金利の下がり過ぎを抑える設計が望まれる。
心配されるのは急激な円高が進むとマイナス金利が深掘りされる可能性があることだ。外資系証券会社は、仮に0.1%深掘りされれば地域銀全体の本業利益が赤字に転落すると試算する。加えて格付け機関による邦銀の格下げにつながれば、外貨調達コストが急上昇する恐れも出てくる。明らかに金融システムを不安定化させてしまう。
日銀は長引く異次元緩和が金融機関の貸出に与えた影響も見定めるべきだ。不動産やミドルリスク企業への融資など過度なリスクテイクを招いた側面が否めない。景気悪化時は融資先の不良債権問題が生じうる。政策対応を考える際はこうした点も踏まえ、あらゆる角度から注意深く検討する必要がある。2019.8.16
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。