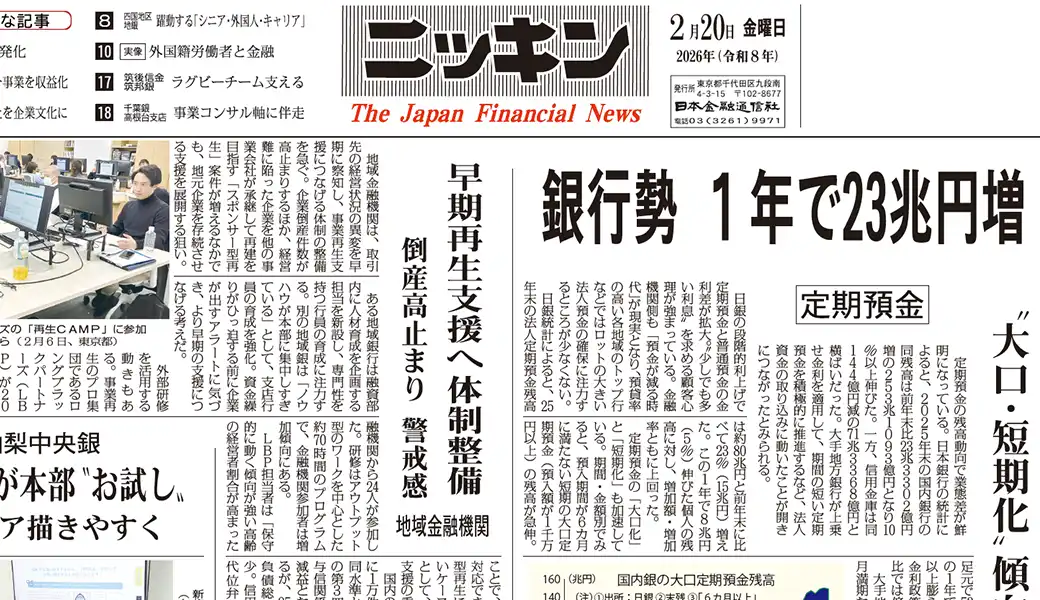社説 備え促し相続トラブル回避
11月15日の「いい遺言の日」から22日まで「夫婦の遺言週間」が続く。超高齢化社会を迎え、相続の増加は確実だ。金融機関は、利用者の相続意識向上に取り組む機会にしてもらいたい。デリケートな問題だけに慎重さは必要だが、相続トラブルを回避するには事前の備えが欠かせない。遺言信託などビジネスとしての取り組みと合わせて、相談会などで相続意識を高めていくことが大切だ。
年間死亡者数は2040年に直近の130万人台から、160万人台まで増えると見込まれている。相続対応で、金融機関が関与する場面も増える。信託協会のまとめによると18年度末の遺言書の保管件数は前年度比約1万件増の13万8千件。18年度に引き受けた遺産整理は6271件で増加傾向は鮮明だ。
ただ、現状では一般の相続に対する意識は必ずしも高いとはいえない。日本財団が17年に行った調査によると60歳以上で遺言を「作成済み」としたのは約5%で、「無関心」が72%に達した。「遺言書を書くほどの財産を持っていない」が主な理由だが、2割は「家族がうまく分配してくれると思う」とし、遺族任せの傾向がある。
こうした現状を踏まえ、金融機関は認知症の進行などを見越して資産の多少にかかわらず「残す人」「受け取る人」双方に、備えを呼び掛けていくべきだ。日本財団の調査では60歳以上の相続経験者のうち2割は相続トラブルを経験している。
事前対策として遺言信託以外に、保険やジュニアNISAによる生前贈与などがある。民法(相続法)が改正され、1月からは自筆証書遺言の利用が緩和されている。財産把握のため、エンディングノートなどの活用を勧めることも有効だ。12年の信託協会の調査では、自己の財産を「すべて把握している」人は2割に満たなかった。
実際に相続が発生した場合の対応も改善の余地はある。静岡県内の金融機関は、預金の相続手続きに関する書類を共通化することを決めた。金融機関ごとに書類が異なり、煩雑という利用者の声は多い。金融界全体の課題として検討が必要だ。2019.11.15
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。