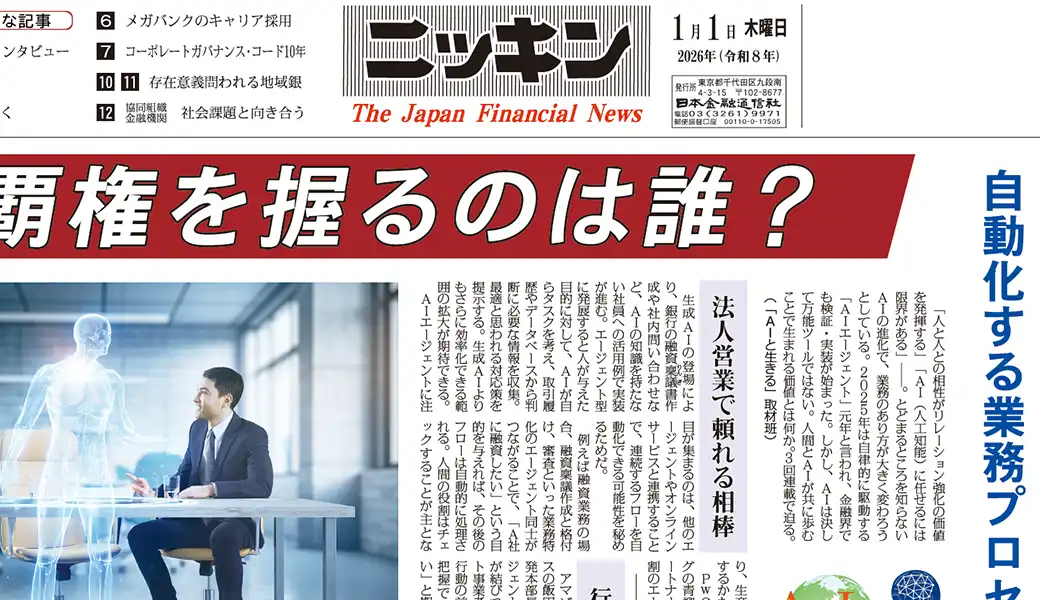社説 認知症対応に外部連携生かせ
全国銀行協会は、認知機能が低下した顧客の預金を親族が代わりに引き出す際の「考え方」をまとめた。医療費支払いなど本人の利益が明らかな場合は出金を認めるとの見解が示され、銀行界でばらつきがあった対応の底上げが期待できる。各行は参考例を基に柔軟な取引を進めてほしい。ただ、認知症の判断や財産保護を銀行だけで行うのは難しい。近隣の福祉機関などとの連携がより重要になる。
認知症顧客の親族から出金を求められた際は成年後見制度など代理人を介する方法があるが、十分に浸透していない。実際は代理権のない親族からの取引依頼が多く、各行は対処に苦慮していた。今回、条件付きで代理権がなくても取引できることが記され、対応しやすくなる。顧客の利便性向上につなげたい。
払い出しに応じる際は、医療介護費など「本人のための費用」であることを確認するのが大前提となる。また戸籍謄本などによる親族の本人確認も怠れない。顧客と接する現場に「本人利益の保護」を徹底する必要がある。
窓口に来た高齢者が認知症かを判断するうえでは、自治体や社会福祉関係機関との連携が欠かせない。「考え方」では地域包括支援センターや地域連携ネットワークなどと「相談しやすい関係を築くことが重要」とされた。
通帳を頻繁になくす、何度説明しても理解できないなどの兆候を、高齢者の日常生活を支える外部機関と共有することで早期対応できる。地域の相談窓口担当者との対話に加え、関係機関が集まる協議会などへの参加も大切だ。
認知症患者の金融資産は2030年に215兆円に達するとの試算もある。財産管理が難しくなれば詐欺被害の危険性も高まり、対策は待ったなしの状況。高齢者を守る地域連携作りに金融機関が積極関与することが求められる。2021.2.26
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。