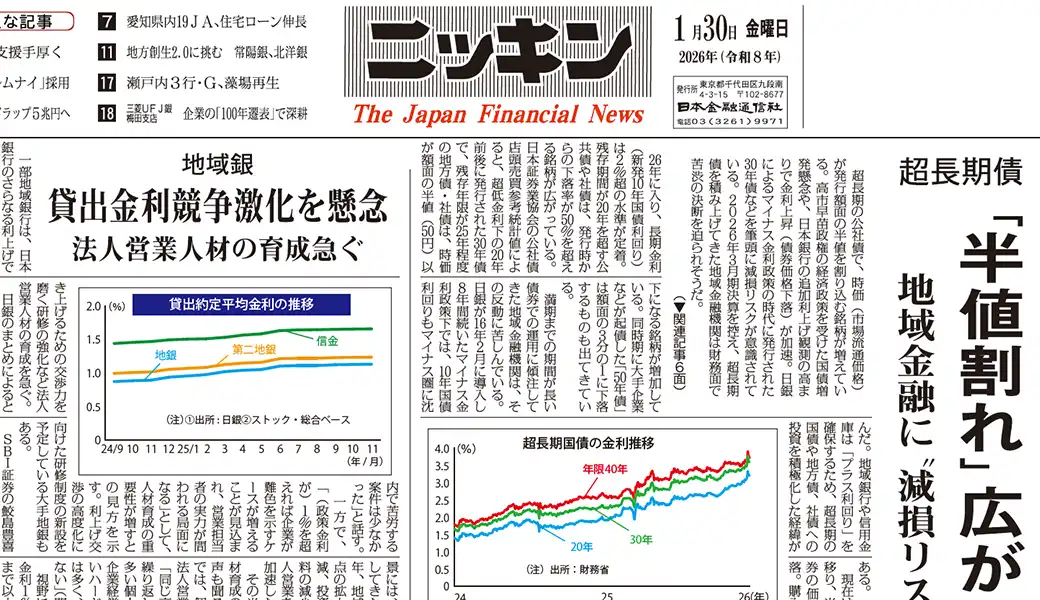社説 デジタル通貨時代を見据えよ
フィンテックスタートアップのJPYCが10月27日から、国内初となる日本円に連動するステーブルコイン「JPYC」の発行を始めた。ステーブルコインには裏付け資産によって複数のタイプがある。JPYCのように法定通貨などを裏付け資産とし、価値が安定するよう設計されたタイプは決済に利用しやく、世界で発行が増えている。国内の送金・決済のあり方を変える可能性があるだけに、金融機関も傍観はできない。
ステーブルコインは暗号資産の一種だが、JPYCは国内の法規制に従って資金移動業者の登録を行い、電子決済手段として発行する。1JPYCを1円で固定。購入者は、いつでも円に交換可能だ。ブロックチェーン上のサービスを使って世界中に送信でき、コストは1円以下をうたっている。クレジットカードのような加盟店契約は必要とせず、事業者が自由に組み込んで決済手段の一つとして提供できるなど、従来の送金・決済サービスとは大きく異なる。
暗号資産データサイトのDefiLlamaによると世界のステーブルコイン時価総額は足元で3千億ドル(約45兆円)規模に達する。5年で15倍の規模に膨らみ、利用額でみると、国際ブランドVisaの決済額を上回るようになっている。
国内で、どれだけ受け入れられるかは未知数だが、金額の大きい企業間の決済・送金で利用が広がれば、金融機関の既存サービスへの影響は避けられない。企業が決済用に現預金をステーブルコインに換えて保有することによる預金減少も想定される。個人預金にも同様の動きが起きるかもしれない。
3メガバンクは三菱商事の社内決済にステーブルコインを活用する実証実験を始める。金融機関は、トークン化預金を含めデジタル通貨時代のビジネスのあり方を探る必要があろう。目先の収益だけに、とらわれていると中長期的に顧客を失うこともあり得る。2025.11.7
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。