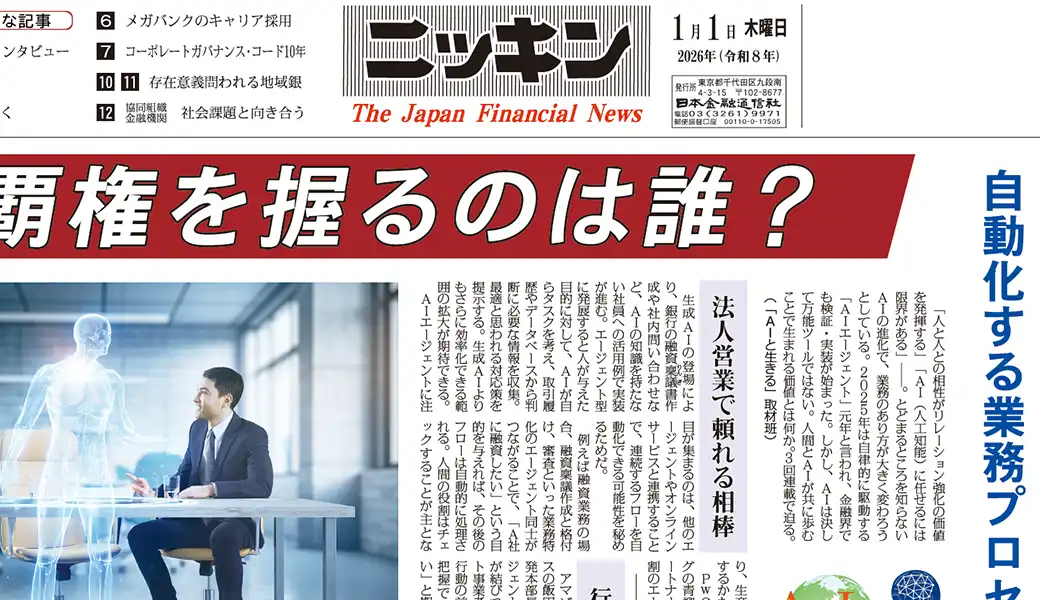社説 現実味帯びる金利急騰リスク
2月21日、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが一時、1.455%に上昇し、15年3カ月ぶりの高水準をつけた。日本銀行の植田和男総裁は、同日の衆院予算委員会で「長期金利が急激に上昇するような例外的な状況では、機動的に国債買い入れの増額を実施する」と発言し、ようやく下落に転じた。だが、利上げ局面に入った日本では、今後も金利上昇圧力が避けられない。金融機関はそのリスクに備える必要がある。 内閣府が2月17日に発表した、2024年10~12月期の国内総生産が市場予想を上回るプラス成長となり、日銀の追加利上げ観測が高まって国債の売りにつながった。だが、そもそもの転機は、日銀が国債買い入れの減額を発表した23年7月にさかのぼる。実際に減額が進むにつれ、長期金利はじりじり上がってきた。 国の借金は1100兆円に上る。財務省は、25年度の政府予算案で長期金利の想定を前年度の1.9%から2%に引き上げ、来たるべき金利上昇に備え始めた。 金利が上昇(債券価格は下落)すれば、国債や地方債などを保有する金融機関の含み損益も悪化する。メガバンクを中心に、国債保有量の削減やデュレーション(元利金の平均回収期間)の短期化を進めてきた金融機関がある一方で、国債依存度が高い地域金融機関もある。危機はいつ起きても不思議ではない。22年に英国で歳出拡大策により金利が急騰した「トラスショック」は記憶に新しい。 いずれ政府にも財政規律が働くはずだと過度に期待するのは禁物だ。25年度予算案の歳出総額は約115兆円と過去最大となった。少数与党の石破茂政権は、予算成立に野党の協力が欠かせない。2月21日、日本維新の会との合意にこぎ着けたが、財政健全化の議論は置き去りとなった。 金融機関のポートフォリオは巨額ゆえ組み換えに時間を要する。再点検を急ぎ危機への耐性を高めねばならない。2025.2.28
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。