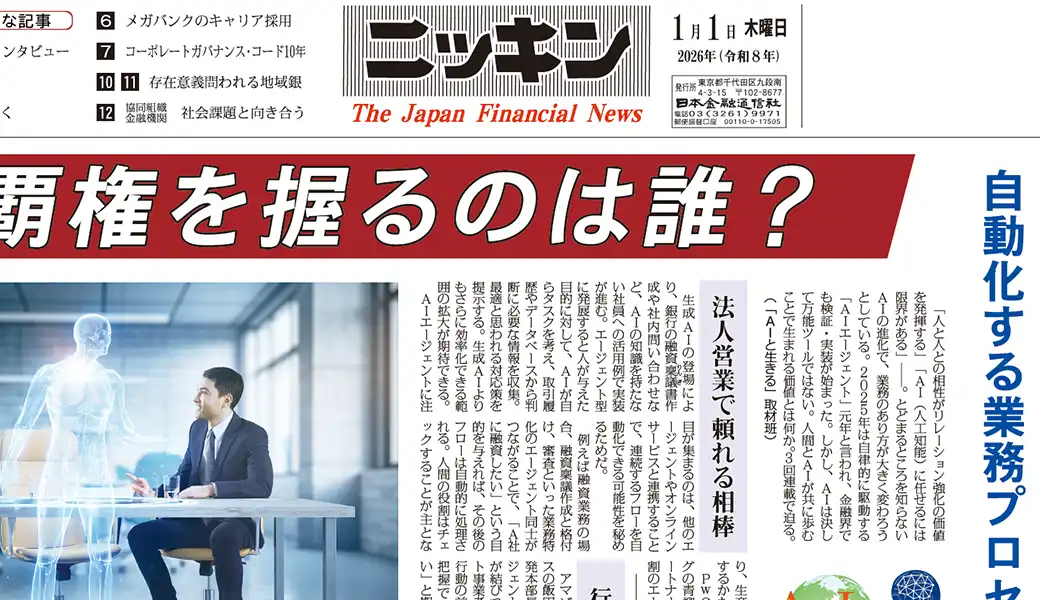社説 踏み込んだ金融緩和の修正を
今回の政策修正は日銀による国債やETF(上場投資信託)の大量購入に伴う市場機能の低下を改善させることが主眼。2%の物価上昇率の達成時期が2021年度以降に後ずれし、政策の持続性を強める必要性が出てきたためだ。市場機能の回復には一定の効果はあろうが、金融緩和の長期化が“宣言”されたことで金利の上昇は不透明だ。
金融機関収益への改善効果はさらに限られる。アナリストの試算では長期金利が0.1%上昇した場合のプラス影響は銀行全体で税引き前純利益の0.7%程度。マイナス金利政策を含む超金融緩和による副作用の軽減には遠く及ばない。日銀自身、金融政策が地域銀行と信用金庫の利ざやを年間0.2%超押し下げていると推計する。緩和が長引くことで金融仲介機能をマヒさせることは許されない。
日銀の財務悪化も無視できない。国債保有が約450兆円に膨らんだ日銀の資産規模は18年3月末に対名目GDP(国内総生産)比で96%と主要中央銀行で突出して高い。結果的に政府は国債の利払い費抑制の恩恵を受けてきており、財政規律を緩めていると指摘されている。さらに基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化目標が5年先送りされたことで、日銀の緩和縮小に制約が強まる可能性も否定できない。
米欧が緩和の出口に向かうなかで日本だけが取り残されている。貿易摩擦などを機に世界的な景気後退局面に入った場合、「次の手」を打てず手遅れになるリスクもはらむ。日銀には市場との対話に留意しつつ、物価目標の柔軟化や出口のあり方に関し踏み込んだ議論を望みたい。2018.8.10
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。