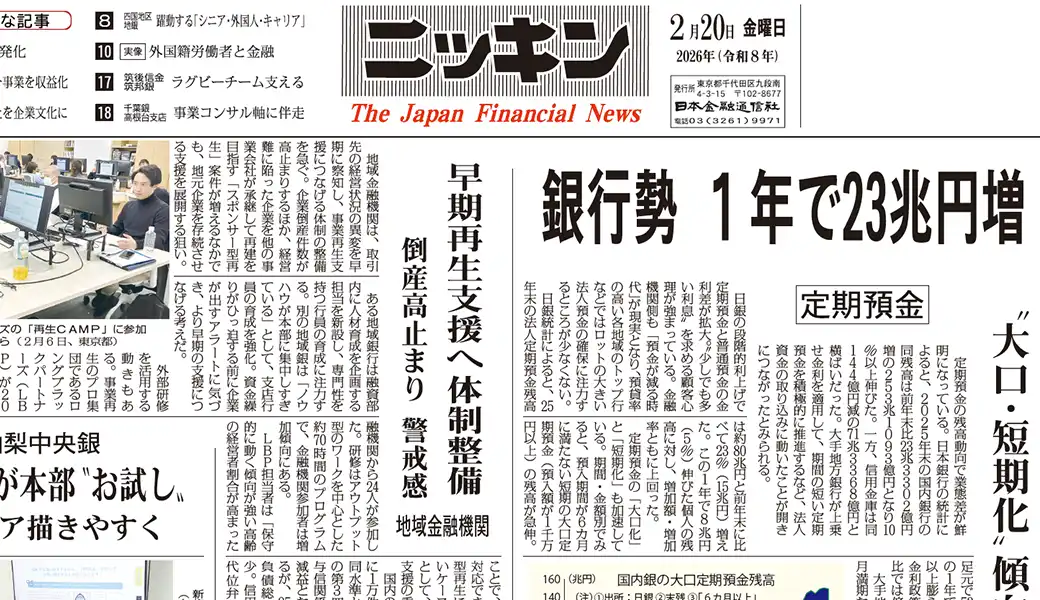ニッキン抄 2021.12.3
この小説を読むと無性にすしが食べたくなる。短編「小僧の神様」は、志賀直哉が後年「小説の神様」と呼ばれるきっかけとなった▼主人公の仙吉は秤屋の小僧。番頭らの世間話を聞き、立ち食いのすし屋が頭から離れない。使いの帰り道、歩きで浮かせた電車賃4銭を懐にのれんをくぐる。だがマグロの握りをつかんだ瞬間、店主に「一つ六銭だよ」と言われ、恥じ入って店を出る▼作品が世に出た大正9年は第一次世界大戦の影響で物価が急騰。大戦景気が成り金を生む一方、庶民の生活は困窮を極めた▼「神の見えざる手」が作用するモノの値段は制御が難しい。コロナ禍で凍りついた経済が動き始め、資源や食品の争奪戦がインフレを招いている。海外では物価の番人たる中央銀行が量的緩和縮小や利上げにかじを切った。日本は企業努力で消費者物価こそ微増だが、10月の企業物価指数は40年ぶり高水準。さて我らが番人はどう難局に処するか。無為無策の神頼みでは困る。2021.12.3
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。