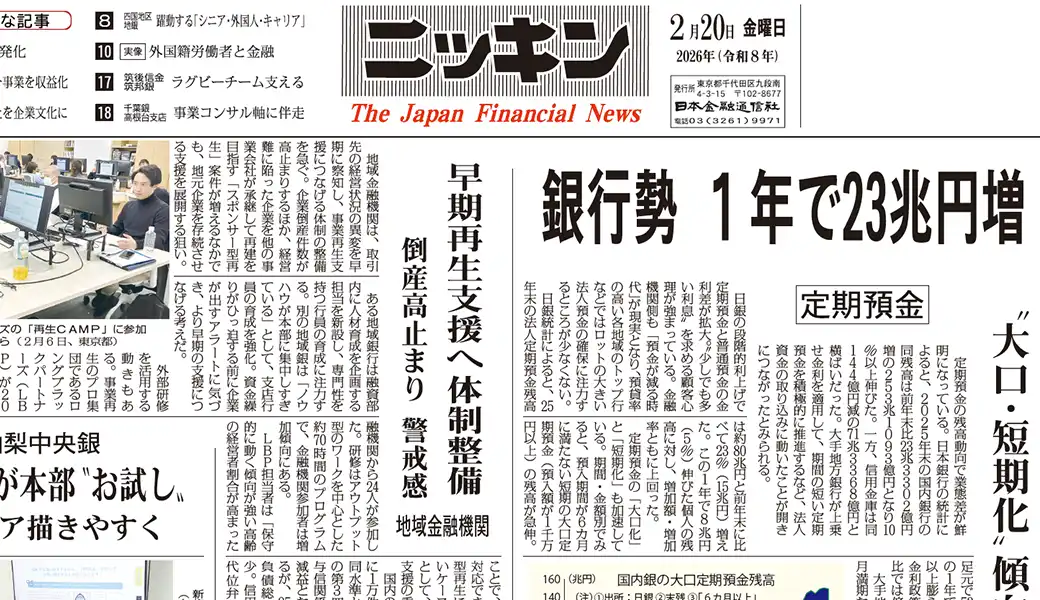社説、金融界の実感乏しい最長景気
政府は1月29日、景気拡大が戦後最長を更新したとみられるとの判断を示した。しかし、「実感を欠く」というのが大方の受け止めだ。とりわけ金融界は、その思いが強い。2012年12月から6年2カ月に及ぶ景気拡大を支える日本銀行の異次元金融緩和は、金融機関収益に深刻な影響を及ぼしている。さらに、限りなくゼロに近い預貯金金利は、退職世代の金融所得を減らし、力強さを欠く個人消費の一因となっている。金融政策頼みから脱却し、経済の足腰を強くしなければ、景気後退期の痛みは大きくなる。戦後最長を素直に喜べる状況にはない。
今回の景気拡大は第二次安倍政権が打ち出したアベノミクス効果だ。目標だったデフレ脱却の兆しが見えてきた点は評価できるが、平均成長率は1.2%で過去いずれの景気拡大期と比べても低く、力強さはない。
顕著な改善がみられる企業収益は金融緩和による円安効果が大きい。その恩恵は大手輸出企業にはあっても国内需要に頼る中小企業などでは限られる。また、超低金利で借入金の利払いが減ったことも一役買っている。その裏側で金融機関が利ざや縮小という、しわ寄せを受けていることは事実だ。
増えた雇用も低賃金の非正規雇用が多い。不適切だった勤労統計が修正され、18年1~11月の実質賃金は9カ月でマイナスだったことも判明し、所得面の「乏しい実感」を裏付けることになった。また、就労しない高齢者は賃金上昇の恩恵を直接受けないうえ、超低金利で利子所得も当てにできず、消費には慎重にならざるを得ない。高齢者の割合が高まるほど、負の影響が大きくなる危うさがある。
現政権は地方創生、一億総活躍、人づくり革命など、看板政策を次々と掲げてきた。いずれも重要課題であり、目は引くが、解決の目鼻をつける前に新たな政策を打ち出し、目くらましにあっている感は否めない。日本経済の持続性や強靭(きょうじん)性を高めるには、中小企業の生産性向上、高齢者がより長く働ける環境整備、女性が真に活躍できる社会など、一つ一つ課題を解決していかなければならない。2019.2.8
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。