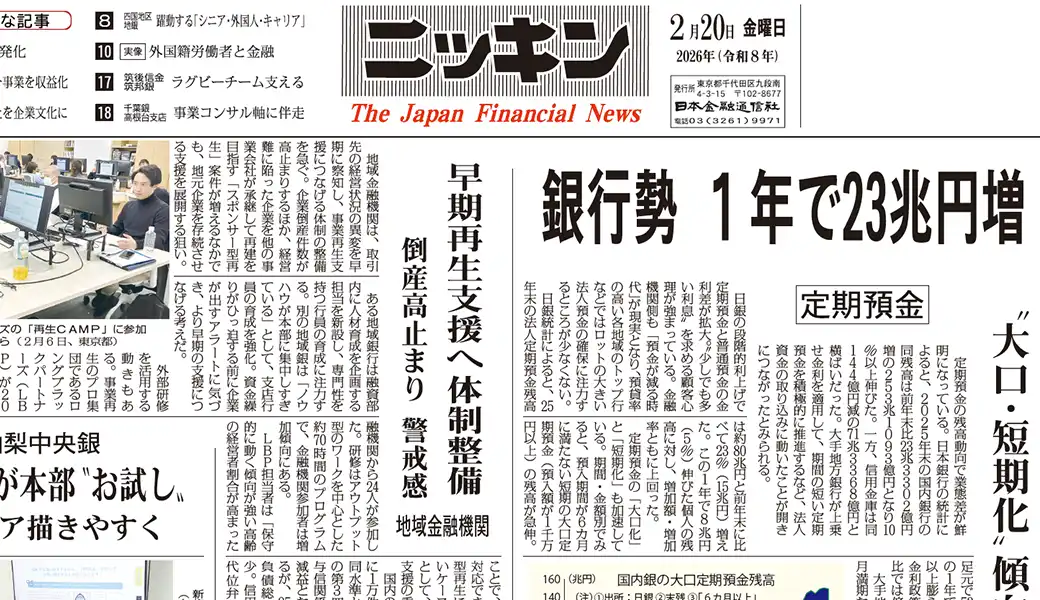社説 指定金問題、地公体も譲歩を
三菱UFJ銀行は、兵庫県芦屋市など複数自治体の指定金融機関を返上する。派出費用や口座振替手数料の引き上げについて、合意できなかったためとされる。収益環境が厳しさを増すなかでの返上に、金融機関の身勝手と受け取られかねないおそれもある。ただ、同行が芦屋市に求めた1件10円の口振手数料は決して高過ぎる水準ではない。金融機関に公共性はあるものの、適正な費用負担は地公体も受け入れを考えるべきだ。指定金業務の採算性改善については、地方銀行を中心に以前から地方公共団体や総務省に強く要望してきた問題でもある。
指定金制度は1964年に導入され、自治体との契約書に「事務取扱上の経費はすべて金融機関負担」とする旨が盛り込まれた。また、以前は貸出や起債業務など指定金に限定された取引があり、金融機関にメリットがあったことも影響し、「無料」という慣行が続いた。
流れが変わったのは90年代後半から。資金取引に入札制が導入され、金融機関は総合採算的な考えが取りづらくなった。2000年に全国地方銀行協会は指定金業務に関する考え方を公表。地公体職員に代わって行員が収納業務を行う派出業務は本来、指定金業務の範囲ではないことや、コンビニエンスストアなどの収納業務に手数料が支払われていることを指摘。04年8月に総務省などへ出した要望書では地銀の窓口収納負担は年間1千億円を超えると推計した。
こうした働きかけで、徐々に派出経費の負担、窓口収納の有料化は実現したが、地公体の収納手数料は一般に比べ低く、採算性は依然厳しい状況にある。コンビニなどとの差も残る。
本来、指定金業務は地公体が自ら行うべき業務を金融機関に委託するものだ。受益者が一定の費用を負担する道理はある。財政状況の厳しい自治体もあり、支出を増やしにくい事情はあろうが、金融機関にばかり負担を押し付ければ、指定金の引き受けを難しくする。また、金融機関は収納事務効率化へ、さまざまな投資も行っており、一方的に負担増を求めている訳ではないことは考慮されるべきだ。2019.3.22
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。