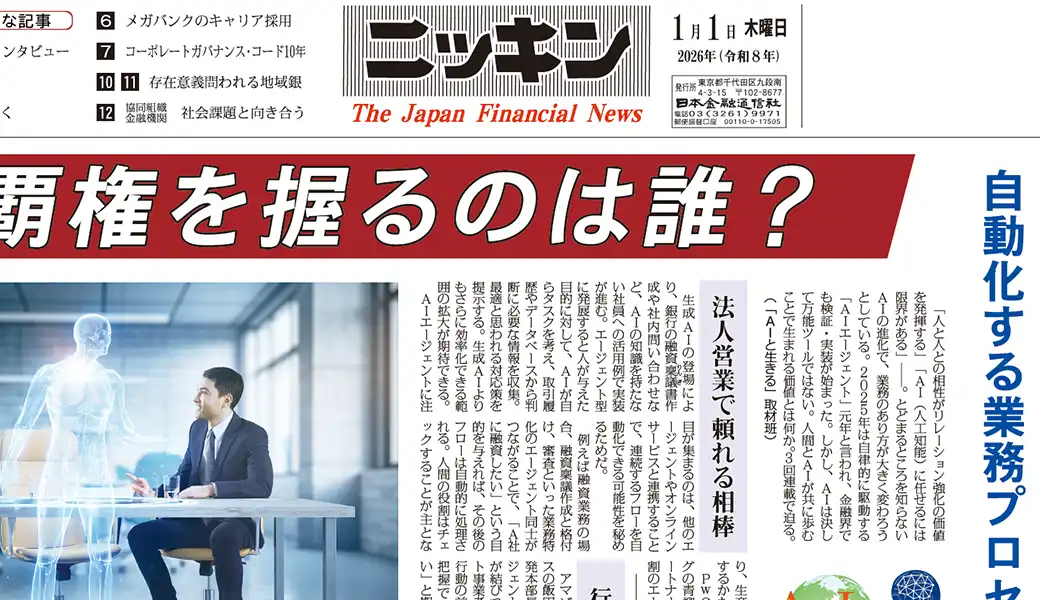社説 パーパスを競争力の源泉に
社会における自社の存在意義「パーパス」を再定義し、経営理念に掲げる金融機関が増えてきた。脱炭素やウィズコロナの顧客支援といった中長期の課題解決に、社員のベクトルを合わせるための基軸が不可欠となっているためだ。不透明な環境だからこそ、パーパスを社内で共有できれば競争力の源泉になる。導入の広がりに期待したい。 先行するのがSDGs(持続可能な開発目標)の世界的潮流への対応が急がれる大手金融機関。三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)は「世界が進むチカラになる。」、三井住友トラスト・ホールディングスは「信託の力で、新たな価値を創造し、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる」と定めた。 地域銀行でも群馬銀行が「私たちは『つなぐ』力で地域の未来をつむぎます」、山口FGも「地域の豊かな未来を共創する」と策定した。持続可能な地域社会を築き上げるという“志”を社内外で共感できるようシンプルかつ明確に表現している。中長期経営計画を策定する金融機関は、それを機に改めて存在意義を見つめ直してほしい。社員のモチベーションも高められる。 パーパスは、企業が果たすべき使命「ミッション」や未来像「ビジョン」に比べ、より社会に貢献するという意味合いが強い。セールスフォースの調査によると、時代に敏感なZ世代では「企業が社会の利益を最優先に行動しているとは思わない」と回答した人の割合が44%を占めた。これからのSDGs世代の信頼・共感を得る手段としても導入する価値は大きい。 もっとも、組織内に浸透させることが重要だ。経営者が機会を捉え社員の腑に落ちるまで対話を重ねる、あるいはパーパスを個人レベルまで落とし込むといった作業も必要だろう。企業風土の変革につなげる視点が欠かせない。2022.3.18
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。