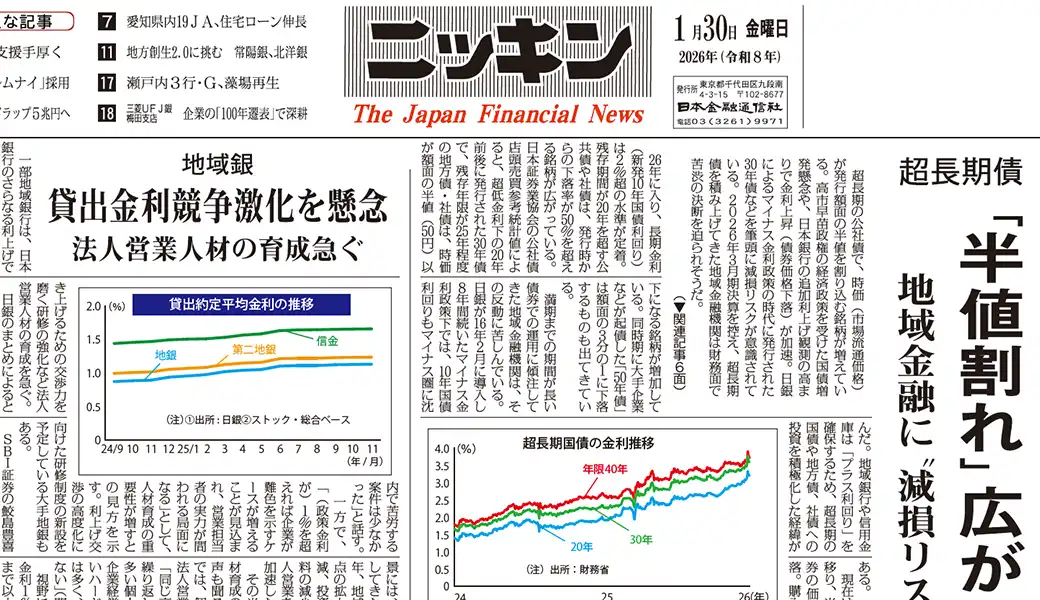社説 評価できる先手打つ選択
新潟県を地盤とし、傘下に第四北越銀行を持つ第四北越フィナンシャルグループ(FG)と群馬県に本店を構える群馬銀行が、2027年4月をめどに経営統合を目指すと発表した。人口減少や「金利ある世界」を踏まえての動きだ。双方の強みを生かして自社だけでなく、地域経済の持続可能性を高める取り組みが期待される。
両者は、ともに県内トップバンクで、足元の経営に大きな問題はない。第四北越FGにあっては傘下の第四銀行と北越銀行を21年1月に合併してから5年足らずにもかかわらず、環境の変化に先手を打つ格好で統合を決めた。その判断を評価したい。前回の統合経験やノウハウは今回にも生かせる点が多いだろう。
一方、群馬銀は貸出などのリスクに対して収益をどれだけ上げられているかを示すリスクアセット利益率(RORA)の考え方を地域銀でいち早く経営に導入し、収益力を高めてきた。持ち株会社方式の越境統合は、店舗の重複が少ないため、経費削減効果を出しにくいとされるが、互いの特長を生かし、株主、顧客、地域、従業員などそれぞれのステークホルダーが実感できる統合効果を示してもらいたい。増える取引先同士をつなぐなど、取引先支援の幅も広げられるはずだ。
地域銀の再編は形を変えながら、じわじわ進んでいる。15年10月に肥後銀行と鹿児島銀行が越境統合し、九州FGが誕生。翌年、常陽銀行と足利銀行も越境統合した。その後は県内合併や、隣県・近県でアライアンスを組む動きが広がった。
共通するのは、確実に進む人口減少への危機感だ。足元で金融庁も持続可能性を切り口に地域銀トップとの対話に乗り出している。地域経済を支える役割を将来も果たしていくための選択を求める圧力は、弱まることはないだろう。浮足立つのは危ないが、立ち止まっていれば、時間的猶予は徐々に少なくなっていく。2025.5.16
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。