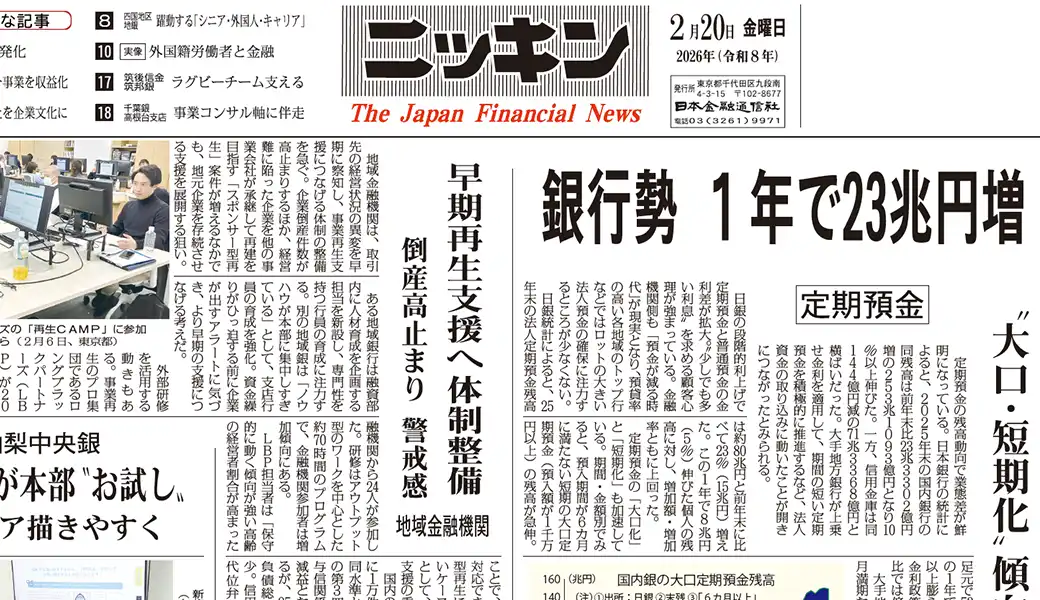3月9日号 新たな正念場迎える被災地
被災地の住宅や道路などインフラ復旧には、ほぼめどがついた。水産庁によると沿岸部の水産業は水揚げ金額ベースで被災前の9割まで回復。再開を希望する水産加工施設も約9割が稼働している。ただ、住民が戻っていないことが被災地の大きな悩みとして残されたままだ。
7年の間に、既に故郷以外に生活拠点を構えた人も少なくない。全国的に人手不足が深刻化するなか、求人・求職のミスマッチも手伝って事業を再開しても思うように従業員を確保できない事態も生じている。同時に住民減少による地元需要縮小が、事業者の自立的な経営再建をより難しくしている。
東京商工リサーチによれば震災関連倒産は震災発生以降、途切れることなく毎月起きており、7年間で1857件、影響を受けた従業員は約2万9千人にのぼる。復興需要が一段落し、グループ補助金を活用した被災企業の業績回復が頭打ちになっているとも伝えられる。
復興・再生には住民が安定的な仕事に就き、住み続けられる環境を整備することが第一だ。金融機関には既存事業者に対する販路拡大など、よりきめ細かな支援に加え、新たな産業創出へ産学官金で協力していくことが求められる。若者の起業を支える取り組みも重要だ。
福島県を中心に原子力発電所事故の影響が色濃く残る。政府は風評被害の解消へ、国際社会へ働きかけを強めてもらいたい。日本産食品を輸入制限する国があるほか、外国人観光客数も他地域に比べ明らかに少ない。政府が定めた復興・創生期間は残り3年。東北創生への歩みを、より確かなものにしたい。2018.3.9
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。