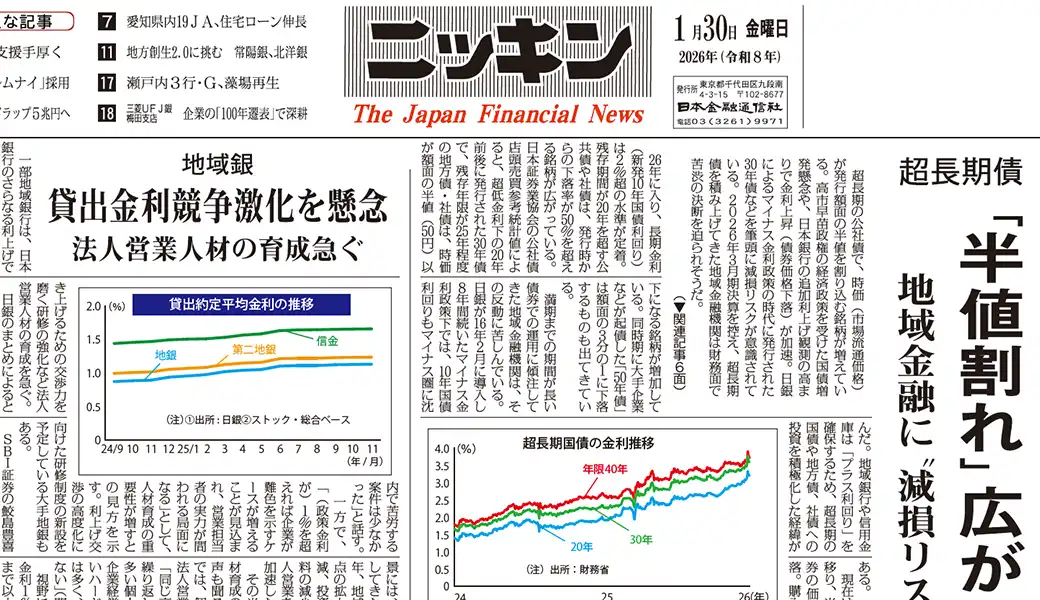社説 「経営者保証」依存から脱却を
企業が融資を受ける際、経営者が連帯保証人になる「個人保証」の存在は、日本企業の成長を妨げる多くの弊害をもたらしている。新たなチャレンジをして、もし失敗すれば、自分の財産まで差し押さえられるかもしれないという心理的な重圧が大きいからだ。個人保証を求める金融機関側にも、経営者の規律に反する行動の抑制や信用リスクの補完など、言い分はあるだろう。だが、人口減少社会が突きつける厳しい環境下で日本経済を下支えする金融機関本来の役割を考えれば、従来の融資慣行を抜本的に見直す社会的要請は極めて強い。
金融庁は11月1日、銀行や信用金庫・信用組合などの監督指針改正案を公表。同庁と中小企業庁は長年にわたり、金融機関に対して個人保証に頼らない新規融資や既存融資の保証解除を促してきたが、改善の動きは広がりにくかった。今回の改正案からは、いまだ多くの金融機関で個人保証を求めることがスタンダードとなっている現状を変えようという強い意志がのぞく。
改正の狙いは、借り入れを行う当該企業の経営者から個人保証を取らない流れをつくろうとするものだ。同庁は11年前にも監督指針を改正しており、その際は経営者以外の第三者の個人保証である「第三者保証」を原則禁止した。当時はまだ、経営者本人の個人保証である「経営者保証」は半ば容認するニュアンスも残されただけに、今回の見直しは大きな転換点となる。
経営者保証の弊害を列挙すると、経営者が新規事業への進出をためらう、過大な保証債務を背負うことを嫌って後継者が見つからない、ベンチャー企業の創業を妨げる、起業家のセカンドチャンスを奪う、など深刻なものばかり。これらは、経営改善支援や事業承継支援、創業支援などに奔走する金融機関自身の課題でもある。すでに自らの判断で保証依存から抜け出した金融機関もある。必要性の有無を再考する契機にしてほしい。2022.11.11
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3237-8124)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。